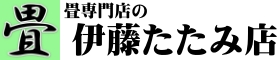畳・敷物の歴史
畳の歴史は非常に古く、日本の住まいとともに発展してきました。
縄文時代~弥生時代
- この頃の住居では、稲わらを敷いていた形跡が多くの遺跡から発見されています。
- むしろやこもといった藁やい草を編んだ薄手の敷物が、畳の原型と考えられます。これらは必要に応じて広げたり畳んだりしていました。
奈良時代(710年~794年)
畳が日本で使われるようになったのは奈良時代です。
- 「古事記」や「日本書紀」には「菅畳(すがたたみ)」「皮畳(かわたたみ)」「絹畳(きぬたたみ)」といった薄い敷物の総称が登場し、畳の始まりを示す貴重な記録とされています。
- 現存する最古の畳は、東大寺正倉院に所蔵されている聖武天皇が使用したとされる「御床畳(ごしょうのたたみ)」です。
- これは、木製の台の上に筵(むしろ)を重ね、さらにい草の菰(こも)をかぶせたもので、錦の縁が付いていました。
- 当時の畳は厚みがなく、主に高貴な人々の座具や寝具として、いわば座布団やクッションのような感覚で使われていました。
- まだ一般的な床材とは程遠い形であり、板敷きの部屋の一部に畳を置いて活用する様子が見られました。
- 当時、貴族は畳を、庶民はむしろやこもを使うのが一般的でした。
平安時代(794年~1185年)
- 貴族の邸宅である寝殿造が広まり、板敷きの床に座具や寝具として畳が部分的に置かれるようになりました. この様子は絵巻物にも描かれています.
- 今日でいう厚みのある畳が登場し, 王朝貴族の豊かさの象徴となりました.
- 身分によって畳の大きさ、厚さ、畳縁の色柄が定められていました. 身分が高い人が座る畳は広く厚みのあるものが用いられ、畳の上にさらに別の畳を重ねたりする習慣もありました.
- 畳は権力の象徴としても機能していました.
床の必要な部分にのみ数枚の畳が敷かれる、「置き畳」のような使用方法が一般的でした. - 京都御所の清涼殿には、平安時代の古い慣習が色濃く残る畳が見られます.
鎌倉時代(1185年~1333年)
- 書院造が確立すると、部屋に畳を敷く面積が増え、やがて部屋全体に畳が敷き詰められるようになっていきました.
- それまで客をもてなす座具であった畳が、建物の床材になり始めていきました.
- 畳職人は「畳差(たたみさし)」や「畳刺」と呼ばれるようになったと言われています.
室町時代(1336年~1573年)
- 畳が部屋全体に敷き詰められることが定着し, これにより正座をする文化が広まり始めたといわれています.
- 茶の湯が盛んになり、畳の上で茶を点てる「茶室」が生まれます.
- 桃山時代から江戸時代へと移るに従い、「草庵風茶室」が発達し、茶道の発達に伴い数奇屋風書院造に変わりました.
- 炉の位置により畳の敷き方が変わり、日本独自の敷き方(祝い敷き、不祝儀敷きなど)が行われるようになったと言われています.
- 畳職人は「畳大工」と呼ばれるようになりました.
安土桃山時代(1573年~1603年)
- 茶道が発達し、茶室の意匠や手法を取り入れた数寄屋風書院造が登場しました。炉の位置により畳の敷き方が変わる手法も広まりました。
- 武家屋敷には床の間が現れ、権威を演出する場となりました。
- 綿ぶとんが普及し、町家や農村でも畳が使われるようになりましたが、まだ貴重品でした。
江戸時代(1603年~1868年)
- 畳そのものが重要な建築物の要素として一般化し、「御畳奉行(おたたみぶぎょう)」という江戸政府の役職が設けられ、江戸城内の座敷や役所の畳を管理し、畳作りや畳表替えの役目を担いました. 畳は特に将軍や大名にとって重要なものでした.
- 庶民に畳が普及していったのは江戸時代中期ごろからと考えられ, 「畳師」や「畳屋」という畳専門の職人が登場し、畳の製作・修繕が盛んに行われるようになりました.
- 当時は家を引っ越す時に畳も持っていく習慣がありました. 江戸時代の長屋では、畳は長屋を借りる店子が運び込んで使ったと言われています.
- それまでは自然に生えていたものを用いていたい草が、岡山や広島などで本格的に栽培が始まりました.
- 各藩の特産物に畳床が登場しました.
明治時代(1868年~1912年)
- 畳の規制(畳縁の柄)が解かれて、一般社会に広く普及しました.
- 文明開化の影響で洋風の家具や調度が取り入れられ、畳の上に椅子が置かれるなど、和洋折衷の暮らしが広がりました.
- 畳干しをこまめにして、傷むのを防ぎ、表が焼けたら裏返しをして使うという習慣が広まりました.れられ、畳の上に椅子を置くなど和洋折衷の暮らしも見られました。
大正・昭和時代(1912年~1988年)
- 洋室と和室が混在する家が増加しました.
- 第二次世界大戦後、高度経済成長とともに日本の生活様式が洋風化し、床材には畳の代わりにフローリングが多く用いられるようになっていきました. 建物構造や消費者意識の変化などによって和室が減り、畳の需要も減少の一途をたどりました.
- 生活様式の洋風化が進み、フローリングが普及し、畳の需要は減少傾向となりました。しかし、畳の機能性が見直される動きもありました。
現代(平成時代~:1989年~)
- フローリングの不便さが見直され、畳の断熱性・防音性・快適性などが再び注目されるようになりました.
- フローリングに敷いて使用する「置き畳」など畳の新しい製品が普及しつつあります.
- い草の代わりに和紙や樹脂を用いた畳や、縁無し畳、カラフルなデザイン畳などが登場し、現代のライフスタイルに合わせて進化を続けています. 洗える畳、カラー畳、ヒノキの畳など多様な畳が登場しています.
- 畳表の素材も従来の藺草やわらだけでなく、新しい化学素材が使われることも増え、耐久性や手入れのしやすさが向上しています.
- 一方で、畳の製造や畳屋の数は減少しており、後継者不足が課題となっています.
このように、畳は時代とともに形状や用途を変化させながら、日本の文化と深く結びついてきました。現代においても、その機能性や日本文化の象徴として、様々な形で受け継がれています.